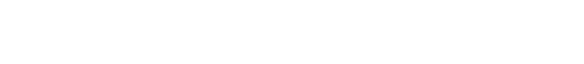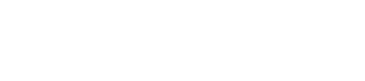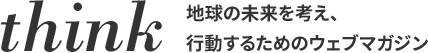contents
ベルリン映画祭が映し出す、ドイツが抱える難民問題のジレンマ
 © Benedict Neuenfels
© Benedict Neuenfels窮地に立つ人に優しい顔を見せたことを謝罪すべきだというなら、それは私の国ではない。
2015年、自身の難民政策についてドイツのアンゲラ・メルケル首相が述べた言葉です。
そしていま。2月25日に世界中から33万人という観客を集めた、第68回ベルリン国際映画祭がその幕を閉じました。様々な問題に頭を悩ませ、揺れる人々の“いま”を伝える多彩なラインナップの中で、激しく心を動かされる映画に出会いました。
「Styx ステュクス」。ギリシャ神話に登場する“死の川”の名を冠した、ドイツ映画です。
物語の主人公は、救急医のリケ。豊かな自然が残るアセンション島で休暇を過ごそうと、一人で小さなヨットを運転してジブラルタル海峡を出発します。目の届く限りに広がる、深く青い海と強い日差し。大西洋に浮かぶこの世の楽園を目指して、進む船。しかし美しい自然は突如牙を剥(む)き、船は激しい嵐に巻き込まれてしまいます。
 ほぼ全編を海上で、船の中で撮影した。ドイツ映画特有の「室内劇映画(カンマーシュピール)」でもある。「自然の猛威の前には人間は無力なんだと実感させられた」と、監督 © Benedict Neuenfels
ほぼ全編を海上で、船の中で撮影した。ドイツ映画特有の「室内劇映画(カンマーシュピール)」でもある。「自然の猛威の前には人間は無力なんだと実感させられた」と、監督 © Benedict Neuenfels激しい波に揉まれ、一人で雨風と戦うリケ。嵐が過ぎ去り、ほっとして、周りを見渡した彼女は、こぼれる落ちるほどに難民を乗せて沈みかかっている漁船を見つけるのです。すぐに無線で緊急救助要請を呼びかけた彼女ですが、彼女の船は小さすぎるので救助は許可できない、手出しをするなと言われてしまい、周囲を行き交う大きなコンテナには、仕事中のために救助は無理だと、断られてしまいます。迷いながらも、目の前で溺れそうになっていた少年を救い上げた彼女。少年は息を吹き返すと、リケに家族の救助を懇願するのですが……。
 リケを演じたズザンネ・ヴォルフ(2018年5月日本公開予定〜「男と女、モントーク岬で」助演など)。実際に小型船舶の免許も持っているという彼女は、ほぼセリフのないこの役を、体で演じきった © Benedict Neuenfels
リケを演じたズザンネ・ヴォルフ(2018年5月日本公開予定〜「男と女、モントーク岬で」助演など)。実際に小型船舶の免許も持っているという彼女は、ほぼセリフのないこの役を、体で演じきった © Benedict Neuenfelsコメントもモノローグもないドキュメンタリーのような映像は、主人公リケの困惑、悩みに観客を巻き込みます。
監督のヴォルフガング・フィッシャーが、この映画のプロジェクトを進めたのは、難民問題がここまで大きく取り沙汰される前だったと言います。「“地中海ルートの封鎖”は、問題の解決にはなりません。封鎖しても、違いはカメラがそこにないというだけで、人が死んでいくことには変わりありません」
 この映画が長編2作目となる、フィッシャー監督。「難民の少年を演じたギデオンは、アフリカ最大のスラム「キベラ」に住んでいます。今年の映画祭審査員長でもあるトム・ティクヴァ監督夫妻が、2008年にケニアに開いた「One Fine Day」という、スラムに住む子どもたちにクリエイティブな活動の機会を作る団体を通じて、彼と出会いました。ほかにもボートの撮影など、色々協力してもらったんですよ」 © Marc Comes
この映画が長編2作目となる、フィッシャー監督。「難民の少年を演じたギデオンは、アフリカ最大のスラム「キベラ」に住んでいます。今年の映画祭審査員長でもあるトム・ティクヴァ監督夫妻が、2008年にケニアに開いた「One Fine Day」という、スラムに住む子どもたちにクリエイティブな活動の機会を作る団体を通じて、彼と出会いました。ほかにもボートの撮影など、色々協力してもらったんですよ」 © Marc Comesこの映画の主人公が直面する問題は、日常の中でも起こりうると監督は言います。「例えば地下鉄の中で、隣の人がけんかを売られているとか……。私たちが望んだわけではなくても、なんらかの行動を起こさなければならない、抜き差しならない状況に陥ってしまう。見ないようにするーというのも行動の1つでしょう。この映画と似たような状況に陥った人を知っていますが、その時彼は、急いでそこから離れたそうです。助けられないと、分かっているからと。その気持ちは、わかります。しかし、この主人公リケは医者です。人を助けることに対して、強い義務感を感じているのです」
この映画は、映画祭の観客賞、第2席を受賞しました。多くの観客が、彼女の痛みや苦しみを、まるで自分のことのように生々しく感じたのではないかと思います。私も、映画が終わってもしばらく席を立てなかったほどでした。
目の前にいる人だけであっても助けたいけれど、自分の力では助けきれないジレンマ。そこに悪意はなくとも、様々なルールや役所の決まりごとに振り回され、人の命を助けるという、根本的なところがおろそかにされてしまっているー。
ふと思い出したのは、昨年出会ったアフガン難民の少年の顔でした。2015年に難民の大規模な受け入れを表明したドイツでしたが、難民の数の多さや、国の右傾化を受けて、アフガニスタンを「安全な国」とし、アフガン難民の本国への強制送還を行なっています。親族を紛争でなくし、命からがらに逃げてきたドイツで、大学に行くことを夢見ながら難民収容所で語学を勉強していた彼。しかし滞在許可の取得が難航するままに、こんどは突然ルールが変わり、本国への強制送還が待っているー。「アフガニスタン出身だからさ、もう無理かな」と、その寂しそうな笑顔が、忘れられませんでした。
この映画の主人公、リケが直面したジレンマは、きっとドイツに住む多くの人たちー世界中の人が抱えているものでしょう。
ドイツ ベルリン在住 東京出身。2000年からベルリン在住。ベルリン美術大学在学中から、ライター活動を始める。 現在雑誌『 Pen』や『 料理通信』『 Young Germany』『#casa』などでもベルリンやドイツの情報を発信。テレビのコーディネートも多数。http://www.berlinbau.net/