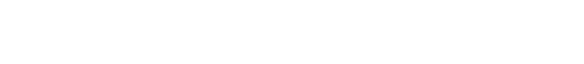contents
ポストヒューマン時代をどう生きるか
このところ毎日のように、人工知能や機械学習に関する話題を聞く。人工知能というと、なにやらロボットや機械のようなものを思い浮かべる人が多いかもしれないが、現在急速に発展しているのは、人工知能というよりもむしろ「計算知能」というべきものだ。
深層学習にせよ、強化学習にせよ、それが今日のコンピュータで実現できるのは、そのアルゴリズムをプログラム言語で記述し、実行しているからに他ならない。コンピュータが行っている計算とは、コンピュータのメモリ上のビットによって表現された数を、あるルールで操作することで数学的に意味のある結果を出力することである。もう少し一般的にいえば、数や文字を表す情報を、アルゴリズムという命題にしたがって、演繹的に実行することが「計算」である。
計算知能が示しているのは、この計算という一見無機的な手順によって、人間や動物一般が行なっている思考や知性を、計算によって具現化、外在化できるということだ。「ものを考えること」や「判断すること」は計算によって実現できる。それはつまり「思考や知能は計算の一種である」ということに他ならない。
今日のコンピュータや人工知能システムは、まだ完全に自律して動くわけではない。だから「知能とは計算である」と言ったとしても、それはコンピュータ単独ではなく、コンピュータと人間がつくる系全体が、その知能の主体であると言うべきだ。
人間とコンピュータの両者が有機的につながっているシステムは、サイバネティックスを自然に想起させる。「生物が感覚器を通じて外界から情報を獲得し、大脳中枢で処理し、効果器、すなわち手足の筋肉系の行動になって再び外界に働きかける過程は、機械のシステムと同じ次元で議論出来る」というサイバネティックスを提唱したアメリカの数学者、ノーバート・ウィーナー(1894〜1964)の主張*1は、そのまま生物と機械を逆にして、「コンピュータが外界から情報を獲得し、CPUで処理し、さまざまなデバイスによって再び外界に働きかける過程は、人間の思考と同じ次元で議論出来る」と言い換えることができる。人工知能とは、「逆サイバネティックス」であるとも言えるのだ。
知能が計算であるとすれば、逆にその計算を拡張することで、知能を拡大することが可能になる。デジタルコンピュータによる数値的な計算以外にも、化学物質や生物、量子や光子を用いた「自然計算」というアンコンベンショナルな(因襲にとらわれない)計算の可能性が探求されている*2。
確かに今日行われている高速大規模計算のほとんどは、デジタルコンピュータが行う数値計算である。計算=人工、と多くの人は思っているかもしれないが、数値計算という機械計算や人工計算をこの自然計算に置き換えることで、計算知能の可能性は大きく拡がっていく。
実際、僕も参加している「自然知能研究グループ」*3は、この自然計算を活用した新たな知能の実現を目指している。例えば、今年2月にアンスティチュ・フランセ東京で開催された第6回「デジタル・ショック—欲望する機械」で展示した「棒知能」*4は、綱引き原理による効率的な意思決定の計算原理を、自走する棒とそれを制御するコンピュータによって物理的に実装したもので、モノ(棒)とコンピュータのサイバネティックスとしての人工知能ということもできる。
ポストヒューマン時代とは、ヒューマン時代に人間を中心に考えて来た常識や、身についてしまった慣習をもう一度見直そうとすることから始まる。
例えばこの「計算知能」を道具という観点から見た時、その一番の特徴は、それが人間の身体や知性の延長線上にはない、ということだ。なぜなら、暗算や筆算という人間の計算方法や自然の計算方法と、コンピュータの計算方法は、本質的に異なっているからだ。
異なる身体や異なる環境から異なる知性が生まれるように、異なる計算からも異なる知性が生まれる。ポストヒューマン時代は、既存のヒューマンを前提としない。人間中心主義から脱出し、人間を強化するのではなく、人間と違うものを許容し、共存する。身体の延長ではなく、擬人化することもできない道具や知性との生態系を構築する。
テクノロジーが現実の反映であったように、人工知能は他者による人間の反映である。他者というのは、こちらの都合にかかわらず、良いところも悪いところも区別なく写し取る。それは人間にとっては、とても厳しいことではあるが、そもそも自然だって、美しいものである前に厳しいものなのだから仕方がない。
90年代、パロアルト研究所の技術主任であったマーク・ワイザー(1952〜1999)は、普段は背後に隠れているコンピュータが、必要な時だけ表に現れて活用できるような、自己主張しない穏やかな技術「カーム・テクノロジー」を提唱した*5*6。今日のIoT(モノのインターネット)にも繋がるこの考え方は、技術と人間の双方が、背景と前景、あるいは周辺と中心の間を自在に移動することを重視する。
彼が示した「メインフレーム」「パーソナル・コンピュータ」「ユビキタス・コンピューティング」という3つの時代区分は、そのまま人工知能技術にもあてはまる。現状はまだ、多くの人がGoogleのような大きな知能を多くの人が共有するメインフレームに相当する時代であるが、やがて個人個人が固有の知能を活用するパーソナル・インテリジェンスの時代へと移っていき、程なく環境に埋め込まれた無数の知能が人間を「共有」する、穏やかなユビキタス・インテリジェンスの時代が到来するだろう。
それはまさに、人間とは異なる知覚や身体を持った環境としての汎知能が、生物・無機物を問わずすべてのものに、まさにアニミズムのように遍在している世界だ。そこでは、人間を含む多様な知能が、一種の知的生態系となって、サイバネティックスのように相互にかかわりあいながら有機的に活動している。
*6 Mark Weiser and John Seely Brown “The Coming Age of Calm Technology” 1996.
ヒューマン時代に世界中の多くの人間が体験した「自分が自分でいられる自由」は、そんなポストヒューマン時代には、どういうかたちで実現しているのだろうか。「サピエンス全史」を執筆したノア・ハラリの新作「ホモ・デウス」*7は、人工知能という意識なき知性の発達により、人間は科学技術によって進化した「ホモ・デウス(神の人)」と「無用層」の2つに分かれるという、マクロに見た人間の未来を予言する。
しかし無用であることは、本当に不幸なことなのか? 逆に無用になることで、人間は近代の労働から解放され、例えば「アリとキリギリス」の寓話における、アリからキリギリスへと転生できるかもしれない。キリギリスは確かに労働は行わなかったかもしれないが、音楽を奏でたり、歌を唄うことで、世界に文化や芸術をもたらしていた。
生命科学や情報技術によって人はポストヒューマンへとアップグレードしたとしても、人が人である限り、そこにはかつて(ヒューマンの時代に)個人や生活と呼ばれた、ミクロに見た人間にとっての自由の場が必要だ。
1897年に「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」という1枚の絵画を、南太平洋のタヒチ島で描いた画家ポール・ゴーギャンの問いは、人間にとっての永遠の問いのひとつである。少なくとも人間ひとりひとりの存在は、有用性ーつまり役に立つかどうかでは定義できない。
ユビキタス・インテリジェンスの時代とは、人間一人ひとりが、自己の存在を超えた何ものかと共に生きる世界である。歴史を振り返れば、人が自分のことを万能であると過信し、何かを支配しようしたり、正義をかざそうとした時に、多くの過ちが起こってきた。ポストヒューマン時代のユビキタス・インテリジェンスは、私たちにもう一度、夢や願い、恐れや畏怖、寛容や折衷という理性の意義を再認識させてくれるだろう。
久保田さんのヴィジョンをもっと知りたい方へ
『遙かなる他者のためのデザイン ー久保田晃弘の思索と実装』 BNN新社(2017)
『ロードアイランド・スクール・オブ・デザインに学ぶ
クリティカル・メイキングの授業』 BNN新社(監訳 2017)
ポスト人間中心時代の理性によるデザイン(2017)
未来から逆算するインタフェースの可能性(2016)

久保田晃弘(くぼた・あきひろ)
メディアアーティスト/研究者
1960年生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授/メディアセンター所長。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。 「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)。近著に『遙かなる他者のためのデザイン ー久保田晃弘の思索と実装』(BNN新社, 2017)がある。
http://hemokosa.com
※写真はLive Codingパフォーマンス中の筆者