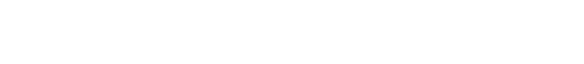contents
「いのち」を核とする未来社会へ
わたしたちは、「生命原理」を、つまり「いのち」を中核に据えた社会に立ち返る必要があるのではないでしょうか。「いのち」ある社会になるためにも、医療を含む社会全体がそうした方向へ向かっていく必要があると思うのです。
今、自分には、4か月になったばかりの赤ちゃんがいます。赤ちゃんを毎日観察していると、小さい命が1日1日を生きることにどれほど切実に向き合っているか、1日1日を必死に命がけで過ごしているのかと、強く感じます。いのちがむき出しで、生きています。
赤ちゃんの時期は、わたしたち生きとし生きるもの全員の原点でもあります。そこに人種や宗教や民族の違いはありません。いのちのはじまり、いのちのルーツ(根)に立ち返るために、赤ちゃんが過ごしている時間について、改めて考えてみたいと思います。
誰もが弱さを原点に持っている
赤ちゃんは、眠っているか、起きてバタバタと手足を動かしているか、泣いているか、このサイクルをグルグルと繰り返して一日を送っているように見えます。赤ちゃんは生き延びることを最重要テーマとして過ごしているようです。
眠る時間は、生命にとって極めて大事な時間です。わたしたちは起きて意識が外に向いている時間だけではなく、眠りによって意識が内側へ向かう時間を必要としています。
起きている時は、外界の風景を見て、外の音を聞いて、匂いを嗅いで、舌で味覚を感じて、全身の皮膚で触れる。無意識でそうした何気ない活動をしているだけでも外から無限に近い情報がやってくるので、それぞれの情報に対して、生命にとって安全なのか危険なのか、命にかかわる問題なのかそうではないのか、一瞬一瞬判断して対応し続けなければいけないのです。そうした果てしない外界の対応に明け暮れていると、ヘトヘトになります。だからこそ、生命には強制的に休ませる仕組みが必要で、「眠り」という休息の時間が生命活動の前提として設定されているのです。
本当は、眠ること自体も命がけの行為です。なぜなら、眠っているときは極めて無防備で、外で何が起きているのかが全くわからないからです。人間には極めて無防備な眠りが必要であることを考えても、人間は必ず誰かの守りや愛を受けないと生きていけない、ということが分かると思います。
眠りから覚めると、赤ちゃんが全くの静止状態であることはほとんどなく、何かしらバタバタと手足を動かし、目や口を動かしています。赤ちゃんは自分ひとりでは全く移動することができません。移動したくても移動できない状況が数か月も続きながら、それでも必死に全身を動かし続けています。大人であれば完全介護といわれる状態ですが、全員がそうした不自由な状態から人生の幕を開ける、ということを今一度考え直す必要があると思います。
赤ちゃんはよく泣きます。泣いているときはお乳やミルクをほしがっている時、おむつを替えてほしい時が多く、もちろんどうとも説明できない理由で泣いていることも多いでしょう。ただ、食事と排泄は自分だけではできません。食事が与えられないと死んでしまいますし、排泄のケアをしてもらえないと感染症などで死んでしまうかもしれません。食も排泄も、命に係わる切実な問題です。だからこそ、必死に泣きわめいて、必ず近くにいてほしい、見守っていてほしいと、私たちに全身全霊で伝えています。
すべての人の原点には、自由に移動できず、食事も排泄もできず、泣いてしか伝えることができない無力な時期があるのです。誰もが、無防備で家族や他者の愛や助けを必要とする時を経て大人になるのです。こうした過去を忘れてしまうと、自分がいま当たり前のように生きていることを忘れてしまい、生きている実感から遠くなってしまいます。誰もが弱さを原点に持っていることさえ共有できれば、社会はもっと優しいものに戻れると思います。
「病」と戦う西洋医学の限界
わたしは西洋医学の医師として日々働いています。病院には、心のバランスを崩した方、体のバランスを崩した方、色々な方が来られます。医師として働く中で、困っている人の助けになりたい、という思いが根底にあるため、心と体に関わることをあらゆる方面から偏見なく追求してきました。相手のためになり、心と体の深い理解に至るためであれば、西洋医学にこだわることなく様々な領域から学ぶ必要があると感じているからです。
西洋医学は「病」を定義します。「病」が中核にすえられた医療なので、医師が働く場も「病院」という名前になります。理由はどうあれ、病を倒すことが至上命題です。病は侵略者であり悪の存在なのです。その過程では、なぜ病が生まれたのか、病はそもそも何か訴えようとしているのか、など、相手の声に静かに耳を傾け対話する機会には恵まれません。
医療現場では、こういうアプローチだけでは、大きな限界があることも日々感じていました。なぜなら病に勝利し、表面では見えなくなっても、根本原因が変化していなければ、病はまた別の形で何度も現れてくることを日々経験しているからです。心や体のことを学び、医療の歴史を学ぶ過程の中で、西洋医学よりも歴史の長い伝統医療や民間医療では、そもそも全く別のアプローチで心や体へ対応していたことに気づきました。
伝統医療では「健康」を最初に決めます。自分がどこへ向かっていきたいか、目的地を決めるのです。次は、そこへ向けて今何ができるかを主体的に考え、自分が主役となり自分自身の心や体の問題として取り組んでいくのです。「健康」とは「調和」と言い換えることもできます。いま現在の状態が「不調和」か「調和」なのかを、心や体と対話していくのです。細かい病名よりも、いかにして自分自身にとっての調和やバランスを全体的に獲得していくか、ということが大切なことです。
人は誰もがそれぞれの絶対的な人生を生きています。誰かと比較することはできません。全員がオリジナルな人生を生きていますが、心や体に関しても同様です。天から与えられた心や体に最大限の尊重を払いながら、その人にとっての調和を人生というプロセスの中で実現していく。そういう考え方のほうが、より本質的ではないかと思うようになりました。
伝統医療では「体液病理学説」というものが長く信じられてきました。紀元前のアリストテレスやヒポクラテスの説を、ガレノス(西暦200年頃)が発展させたものです。古代ギリシャの時代から伝わるように、当時の人体観では、4つの元素(火・空気・水・土)と4つの体液(黄胆汁質・多血質・粘液質・黒胆汁質)が人体を構成しており、そのバランスが崩れると病になり、そのバランスを取り戻すことが健康に通じる、という考え方を持っていました。4つの根源的な要素が人体を巡り調和させているという考え方は、人体という枠を超えて自然や宇宙の調和へも広がります。つまり、人体を学ぶことは自然や宇宙の原理を学ぶことにも通じていき、ミクロコスモス(人体)とマクロコスモス(宇宙)とはサイズやレイヤーが違うだけで、同じ原理で共鳴しあう、部分と全体であると考えられていたのです。
その後、長くそうした考え方が支配的でしたが、西洋医学の始まりと言われる発見がありました。ドイツの医師であるルドルフ・ウィルヒョウ(1821-1902年)が、「体液病理学説」に対して「細胞病理学説」を提唱したのです。これは、人の体は細胞からできていて、その細胞が病気になることで体の病気が引き起こされる、という考え方です。そのため、病気をまず病理学的に定義し、敵である病と闘い、病を撲滅することで病気を治そう、という発想が生まれることになったのです。
確かに、そうした人体の見方は、感染症や、戦争などで受けた外傷への急性期治療には大きな役割を果たしました。ただ、そこに調和や自然や宇宙という発想は全く用なしとされてしまったのです。そんなことを考える必要はなくなりました。人体を循環しているとされていた4つの元素や体液も物質として同定されないため、間違った考え方として葬り去られてしまったのです。
臨床医としての自分が感じるのは、人体の見方や生命の見方が変わったことで、わたしたちが毎日接している体や心の原理の中に、自然の叡智を感じなくなってしまったのではないかということです。毎日接している体や心から自然の法則を見出し発見しさえすれば、自分自身が地球や宇宙などの原理とも共通していることを感じることができ、自分と自然との深い関係性を日々感じることができるはずだと思うのです。
日本の医療は「美の次元」に深化していた
日本の伝統医療のルーツを知りたくて、日本の医療の歴史をいろいろと調べました。医学史の教科書を読むと、日本の医療にはオリジナルなものはなく、中国医学やインド医学(アーユルヴェーダ)や蘭学、ドイツ医学、アメリカ医学など、海外のものを受動的に取り入れてきた歴史であると書いてあります。
ほんとうにそうなのだろうか、とわたしは疑問に思っていました。医療の最先端の現場で働いているからこそ、温故知新を強く感じるようになり、古代の医療から変わらないであろう心や体の本質をこそ学びたいと思い続けてきました。そのため、わたしは万葉集や古事記をはじめとする古典の世界を読み、お能や謡いや仕舞いを学ぶようにもなりました。伝統の中に培われた身心の深い知恵を学びたいと切実に思ったからです。その結果、今まで見落とされていた、とても重要なことに気づきました。
日本では心や体に関するあらゆる知恵を医療の次元ではなく、「道」や「美」という次元へと高めてきた文化なのではないか、と気づいたのです。「病」を戦争のメタファーでとらえるのではなく、心や体を調和の場であると捉える次元を道標として深化していったのではないでしょうか。それは、藝道、武道、華道、茶道、書道、香道、和歌、舞踊、雅楽、工藝、民藝・・・など、あらゆる伝統や美の領域に渡っています。「道」や「美」という調和の場を目標とすることで、心や体はおのずから整っていくのです。結果として病気がよくなっていることもあるでしょうし、病気がそのままであったとしても、心や体とのよりよい共存・共生関係に至ることができます。
心というものは、表層意識と深層意識とが共存して相補的に調和的な関係性をとり続けています。体というものは、60000000000000(60兆)個のすべて生きている細胞たちが、見えない世界でコミュニケーションをとりながらつねに調和の場を作り続けています。古(いにしえ)の人たちは、そういうことを直感的に感じていたのだと思います。心も体も、どこへ向かうべきか目的地を知っているのです。
自然や生命の本質は多様性と調和です。互いが互いを補い合い、全体として存在しています。それは数十億年に渡るいのちの歴史を包括的に眺めているとよく分かります。自分が一生付き合っていく心や体の問題を、争いや闘いの場としではなく、多様性と調和の場としてとらえていくことは、この社会を多様性と調和の場にしていくことにもつながるのではないでしょうか。
いのちを核とする未来社会では、誰もが「いのち」を持っていることを尊重する、原点に戻る必要があります。それは人間だけではなく、すべての生きものにとっても同様です。お互いの「いのち」を大切にすることは、いのちの原理である多様性と調和を大切にすることでもあります。そして、「いのち」は生まれたときから弱さを含んでいるからこそ、社会的に弱い存在を大切にしながら、お互いが協力し合う必要があるのです。
これからの未来の医療に必要なことは、伝統や過去の中から、新しい視点をもって体、心、命の本質を再発見していくことだと思います。それこそが、亡くなった故人から、生きているものが「いのち」を受け取る、ということでしょう。生きているだけで、すでにバトンを渡されているのです。過去と未来とは、現代に生きている人たちが結び目をつなぐからこそ、バラバラにならずつながっていくのだと思います。
稲葉さんのヴィジョンをもっと知りたい方へ
『見えないものに、耳をすます ―音楽と医療の対話』 アノニマ・スタジオ(2017)
『人生が変わる!無意識の整え方』 ワニブックス(2017)

稲葉俊郎(いなば・としろう)
東大病院循環器内科 助教
1979年熊本生まれ。医師。2004年、東京大学医学部医学科卒業。現在、東京大学医学部付属病院 循環器内科 助教。心臓カテーテル治療や先天性心疾患を専門とし、在宅医療や山岳医療にも従事。2011年の東日本大震災をきっかけに、医療の枠を広げる未来の医療の土台作りために、様々な分野に渡って個人での活動を始める。SWITCHインタビュー 達人達「大友良英×稲葉俊郎」(NHK、2017年3月11日)の対談本『見えないものに、耳をすます ―音楽と医療の対話』がアノニマ・スタジオより発売された。
https://www.toshiroinaba.com