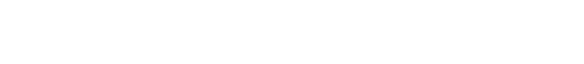contents
森の営みから学ぶ未来の保育とは〜 保育者のエコカレッジ「ぐうたら村」
 近年、保育の世界でもSDGsやESDの視点を持つことが大切だといわれています。持続可能な社会と未来の保育を結んで考えようと、幼児教育や周辺領域の専門家が一緒になって立ち上げた保育者のエコカレッジ「ぐうたら村」を先月初旬に見学してきました。最先端の学びの場なのに “ぐうたら”という、ちょっとズボラなネーミングなのが面白いなぁと以前から気になっていた場所です。
近年、保育の世界でもSDGsやESDの視点を持つことが大切だといわれています。持続可能な社会と未来の保育を結んで考えようと、幼児教育や周辺領域の専門家が一緒になって立ち上げた保育者のエコカレッジ「ぐうたら村」を先月初旬に見学してきました。最先端の学びの場なのに “ぐうたら”という、ちょっとズボラなネーミングなのが面白いなぁと以前から気になっていた場所です。
Contents
■不毛の地を選んだ理由は?
■グランドデザインのない村
■地球は凸凹でできている
■鶏小屋が教えるSDGsとは?
■図鑑を足しても森にはならない
不毛の地を選んだ理由は?
ぐうたら村では、全国の保育者や幼児教育を学ぶ人たちに向け、地域に根ざした素材や技を用いた建築や工芸、農、食のワークショップなどを中心に、幼児保育や周辺領域の専門家によるゼミやセミナーも随時開催しています。場所は八ヶ岳南麓の風光明媚な山里。運営は基本的に会員制ですが、誰でも参加できます。
村長を務めるのは、国内の保育・幼児教育研究の第一人者である汐見稔幸さん。汐見さんは「学びほぐし」というキーワードを村の説明に使っています。私たちはリアルな体験を経なくても、地球上のあらゆる知識や情報に楽にアクセスできる時代を生きていますが、頭でっかちにならず、ここで心と体をリセットしてほしい、そんな願いがあるようです。
 山梨県北杜市の豊かな自然に溶け込むようにあるぐうたら村
山梨県北杜市の豊かな自然に溶け込むようにあるぐうたら村
取材に応じてくれたのは、森の案内人としてゼミやワークショップ、トレッキングツアーのガイドなども担当する小西貴士さん。小西さんは公益財団法人キープ協会で子どもの環境教育に長年携わった後、汐見さんと意気投合してこの土地に保育者有志と村作りを始めて10年になります。
 「未来の社会像は変わっているのに、保育者養成課程のカリキュラムはなかなか変われない。公ができないことは民間で補っていこうという思いが始まりでした」と小西さん
「未来の社会像は変わっているのに、保育者養成課程のカリキュラムはなかなか変われない。公ができないことは民間で補っていこうという思いが始まりでした」と小西さん
「始めは作物が育たない赤土砂漠だったんですよ。ここは戦後、満蒙開拓団が切り拓いた土地で、下の清里高原道路を整備した際に掘り起こした残土をこの地区の畑で受け入れた、と聞いています」
赤土とは、火山灰からなる褐色の土のこと。小西さんは硬い土が残る一画を示して「ここ、触ってみて」と促します。かちかちのビクともしない地面です。人が農を営んできたのは、落ち葉や生物の死骸が降り積もってできる柔らかな黒土層ですが、ここは逆に赤土が顔を出していました。自然界では洪水など大きな撹乱(かくらん)でもないと起きない現象ですが、人は重機で土地を改変する力を持っています。
「こんなふうに地層がひっくり返った場所を環境教育の舞台にしたら、保育者にわかりづらくないですか? 僕は最初反対したんですが、汐見先生は『逆にこういうところで人が丁寧な暮らしを営んだら、人も豊かになるし、他の生命も豊かになっていく。そういう物語が大切になっている時代なんじゃない? それを保育者と一緒にやれない?』と言われて、それは面白そうだと思ったんです」
 村作りはみんなで手を動かしながら、少しずつ行ってきた
村作りはみんなで手を動かしながら、少しずつ行ってきた
グランドデザインのない村

ぐうたら村には、童話の主人公がふっと顔を出しそうな、そんなたたずまいがあります。小屋の屋根から草がひょろっと生えていたり、中をのぞくと、「遠くを見る、足下を見る そして自分を見る それでひとぐうたら」と汐見村長が書いた謎のメッセージボードが立てかけてあったり(笑)、ユーモアを持っておおらかなモノ作りが行われたことが伝わる空間です。
 蒸したトウモロコシの甘い匂いが充満する青空キッチン。赤土を活用したアースバック工法で建てられている
蒸したトウモロコシの甘い匂いが充満する青空キッチン。赤土を活用したアースバック工法で建てられている
 保育者たちが子どもの頃に読んだ漫画本約4000冊を集めて収納した漫画小屋。中学生発案の秘密基地だそう
保育者たちが子どもの頃に読んだ漫画本約4000冊を集めて収納した漫画小屋。中学生発案の秘密基地だそう
聞いて驚いたのですが、村作りはあえてグランドデザインを持たずに進めているのだそうです。勇気と辛抱が求められるやり方です。未来の保育を考えるこの場所にグランドデザインが要らない理由を、汐見さんはこう話したそうです。
「だって、子どもの遊びって総合計画ないでしょ。でも、面白くなるし、発展するし、途中で崩れたりしながらも進んでいく。そのことを一番考えなきゃいけない保育者が学ぶ環境としては、グランドデザインのない場所を作ることが、実は一番してあげられることじゃないの?」
 「10年経ってようやくこのやり方に慣れてきました」、小西さんはそう言って笑います
「10年経ってようやくこのやり方に慣れてきました」、小西さんはそう言って笑います
「要するに完成図がないんです。僕自身そういう教育はあまり受けてこなかったし、社会に出てからもそういうやり方を見たことがなくて。例えば、いつまでここにこれが散らかっているんだろうとか、お金をどうするんだろうとか。はじめは不安過ぎて。何をやっても、大丈夫??って」
子どもと向き合うために保育者が最も大切にしなければならないことを譲らない。そんな大人たちの覚悟が伝わる素敵なエピソードだなと思いました。

去年、賛同者の寄付や仲間の支援を受けて完成したワークショップなども開催できる社屋「ぐうたラボ」も村の基本方針に違わず、今も細かいところを村を訪れる仲間たちとつくり続けています。デザインは、建築家の藤森照信さん。屋根のてっぺんの草、触ると手が黒くなる(笑)焼杉の壁板、森の木をそのまま持ってきたようなくねっとした支柱。一目で「藤森建築!」とわかる個性満載です。
「藤森さんは著名な建築史家ですが、気さくで面白くて、ヒョロヒョロ〜ってスケッチ描いて、作りながらアイデアを練っていく方ですから、僕らにピッタリでした(笑)。完成した建物から感じるのは、見事にこの地に溶け込んでいながら存在感があるということ」
備前の伝統工法である焼杉板は、一枚一枚板を焦がして製作します。その模様を収めた興味深い動画があります。焦がすことで板の耐久性が格段に向上するのだそうです。
焼杉板製作の様子を収めた動画(撮影:モチドメデザイン事務所 持留和也氏)
地元の石を埋め込んだ暖炉の築炉や和紙の照明カバー製作、本棚作り、漆喰塗りなど内装も2年半かけて保育者たちと一緒に進めてきたそうです。薪ストーブの台にする鉄平石を敷き詰めたり、いすの座面を編んだりする作業も、保育者有志が地元の職人さんに教わりながら取り組んできました。
 中に入るとすがすがしい木の香が
中に入るとすがすがしい木の香が
 屋根付きのラボが完成し、遠方から楽しみに出かけてくる保育者に「雨天中止」とがっかりさせることもなくなりました、と小西さん
屋根付きのラボが完成し、遠方から楽しみに出かけてくる保育者に「雨天中止」とがっかりさせることもなくなりました、と小西さん
地球は凸凹でできている
建築、工芸、食など、ぐうたら村ではさまざまなワークショップを行ってきましたが、中でも大きな比重を占めるテーマが自然と農です。
村の畑では、保育者が子どもたちとわかち合いたいことは何なのかにこだわってきた結果、自然農やパーマカルチャーに近いフィールドが出来上がりました。なじみの野菜やハーブも、効率良く植えつけられた畑より生命力旺盛に見えて、歩いて回るだけでも楽しいエリアでした。
 短く切った稲わらや蒸留後のラベンダーの花穂など有機物をマルチング材にして土づくり。今ではふかふかの団粒構造の黒土が出来てきた
短く切った稲わらや蒸留後のラベンダーの花穂など有機物をマルチング材にして土づくり。今ではふかふかの団粒構造の黒土が出来てきた
 一年草の野菜だけにこだわらず、多年草や果樹など多種多様な植物が育つ環境を「畑」と呼んでいる。写真のセイヨウワサビは根で冬越しする多年草。大きい!
一年草の野菜だけにこだわらず、多年草や果樹など多種多様な植物が育つ環境を「畑」と呼んでいる。写真のセイヨウワサビは根で冬越しする多年草。大きい!
 ルッコラの花やルバーブの種、食用部分以外の姿を、私たちは意外なほど知らないものです
ルッコラの花やルバーブの種、食用部分以外の姿を、私たちは意外なほど知らないものです
ここの畑が他とちょっと違って見えるのは、人間の取り分がほどほどだから、かもしれません。種を採るために一部は花まで咲かせたり、人が食べられない植物も植えて多様性を確保します。
「花が咲くと、この子がどんな虫と関係を結びたがっているのかが見えてくる。植物の見方が変わる」と小西さん。相性の良い虫の助けを借りて花は受粉し、種が実ります。収穫をピークと考える人都合のサイクルとは違う、生命循環の物語が見えてきます。
 「子どもの頃はJAの規格に合わせたような生産効率重視の農業は教えなくていいと僕は思う。それより世界どこに行っても通用する生命の原理原則にちゃんと気づける環境を」
「子どもの頃はJAの規格に合わせたような生産効率重視の農業は教えなくていいと僕は思う。それより世界どこに行っても通用する生命の原理原則にちゃんと気づける環境を」

小西さんは、森の話をよく引き合いに出します。人間にとっての利用価値ばかりで自然を見ていくと、森はほぼわからないことだらけ。「これは一体何の役に立つ??」とどんどん息苦しくなってしまいます。
一方、そこにいてくれるだけでいいという価値を生態学の世界では、「存在価値(非利用価値)」と呼ぶそうです。畑には、たくさんの生物がかかわり合う森の知恵が随所に投影されています。人は凸凹を平らにならそうとしますが、「地球は凸凹でできていている」、と小西さんは言います。
 森の植物は水をあげなくてもすくすく育つ。キーホール型ガーデンは、緩斜面の低い方に雨水を受け止める円状の低い堤防を作ってある。水やり不要な森を模した仕組みを試験中
森の植物は水をあげなくてもすくすく育つ。キーホール型ガーデンは、緩斜面の低い方に雨水を受け止める円状の低い堤防を作ってある。水やり不要な森を模した仕組みを試験中
 セリ科のノラニンジンの花。畑にはあえて食用ではない植物も一緒に植え込んである。キアゲハが産卵に飛来する
セリ科のノラニンジンの花。畑にはあえて食用ではない植物も一緒に植え込んである。キアゲハが産卵に飛来する
 モグラの通り道などがのぞける地面のドアも。「好きな時に開けてもらって、地下の生態系にも気づいてほしい。こういうのがもっと学校や園にあってもいいよね」と小西さん
モグラの通り道などがのぞける地面のドアも。「好きな時に開けてもらって、地下の生態系にも気づいてほしい。こういうのがもっと学校や園にあってもいいよね」と小西さん
所々に鎮座する“Bug Hotel”と書かれた物体は「何だろう?」とずっと気になっていましたが、生きもの用のホテルでした。暖炉用の薪を円筒型に組み上げて、上を枝で覆います。薪が必要になったら崩して使いますが、それまでは木材間の絶妙なすき間が虫や蛇、カエルのすみかになるそうです。
 中の様子をうかがうのぞき窓がついています
中の様子をうかがうのぞき窓がついています
 こちらはドロバチや狩りバチの仲間が“入居”(産卵)したばかり(一番下の穴)のbug 小屋。ドロバチや狩りバチの仲間は畑の虫をとってくれる大切なパートタイマー」と小西さん。存在価値を教えてくれる代表格だ
こちらはドロバチや狩りバチの仲間が“入居”(産卵)したばかり(一番下の穴)のbug 小屋。ドロバチや狩りバチの仲間は畑の虫をとってくれる大切なパートタイマー」と小西さん。存在価値を教えてくれる代表格だ
鶏小屋が教えるSDGsとは?
フィールドには人なつこい白毛の烏骨鶏がすむ小屋があります。15羽収容の小屋と、3羽だけの小屋と2つあって、観察すると様子が異なることがわかります。
 15羽の鶏小屋。小屋周辺は鶏が首を伸ばせる位置までぐるっと草が食べ尽くされている
15羽の鶏小屋。小屋周辺は鶏が首を伸ばせる位置までぐるっと草が食べ尽くされている
 3羽の鶏小屋。鶏の数に対してスペースが広く、中まで草の緑が目立つ
3羽の鶏小屋。鶏の数に対してスペースが広く、中まで草の緑が目立つ
15羽と3羽の生息環境の違いは、「環境収容力」をヒントに考えることができると言います。環境収容力とは、ある環境において生物が持続的に存在できる最大量のことで、群衆密度は計測できます。
ここではその飽和状態を目で見ることができます。小西さんは、大所帯の小屋の“アルファ雄(群れのリーダー雄のこと)”に向かって一粒のラズベリーを投げ入れました。すると、即座に近くにいた雌が丸呑みしてしまいました。周りは「今、一瞬食べものを見た気がするけど!」という表情で周りを焦って探しています。
「リーダーは我先にとは食べないんですよ。競争が激化すると種の保存に不利だと知っているんです。仲間に“あるよ、あるよ”とくわえて見せて、それを雌が横から取っていく。鶏にも社会性はある。体格が良く、力が強いアルファ雄が優先して食べることができる社会をつくってしまうと、群れ全体の存続は危うくなっていくということです」
地球上の人類の環境収容力は26.4億人と1930年代に算出されていますが、今の人口はそれをはるかに上回る水準にあります。烏骨鶏のアルファが示してくれたように人類もよっぽど利他を意識した行動をとらなければ、飽和状態のまま生き続けることは難しくなります。
「人間も今、15羽の小屋の鶏のように追い詰められた環境にある。その環境をどうやって群全体で生きていこうかと模索しているのがSDGs時代ですよね。そう考えるとすごくわかりやすい」と小西さんは説明してくれました。
図鑑を足しても森にはならない
2018年、保育所保育指針、幼稚園教育要領などいわゆる3法令が10年ぶりに大幅改定となりました。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」という指針の中には、子どもの自然体験を促す「自然との関わり・生命尊重」という項目もあります。保育に携わる人の多くは、村の取り組みをこの指針と結びつけて見る人も多いでしょう。小西さんはどう見ているのか、聞いてみました。

「自然体験をすると人の育ちにいい。僕は正直まだそこかなぁと思うんです。自然は人間が利用できるものという目がまだ強過ぎる。人間中心の考え方ですよね。人が生きていくために自然が必要、ではなく、むしろ鶏小屋の例でもわかるように、この中(地球)でやっていくしかない。個別の命を見る部分の教育ではなく、森や地球を土台とした全体の教育をもっとデザインする必要があるように感じています。人も大事だけど、地球も大事だよと言える人の声を育みたい」

写真家としても活動する小西さんは、著書『チキュウニウマレテキタ』のあとがきで次のように記しています。
“人間として生きることを学ぶとは、自然体験をすればよいということではありません。心の奥底に、人生は生きるに値するという全幅の信頼を育むことは、ヒトだけによるものでは難しく、もっと全体的だということなのです”
例えば、教育現場では子どもたちに水道の蛇口をキュッと閉めることを通して“今世界の水をめぐる事情は大変で、水資源は大切なんだよ”と伝えますが、小西さんはこう指摘します。
「森には蛇口を閉めましょうなんてどこにも書いてない。森では冷たくて飲める水が実際出しっ放しなんですよ。幼い人には、まずは私たちが生まれてきた地球のことを知って、信頼して、安心してもらいたいんですよ。冷たくて飲める水が出しっぱなしなんだって。その上で、世界の水をめぐる事情が厳しいんだとしたら、『じゃあどうしたらいいんだろう』と考える。そういう順序だと思うんですよね」
「生命や自然に関することは、文字や知識伝達のような客観的な経験のみならず、からだを通した主観的な体験を大人になってからも必ずし続けてほしい。からだを通さない“いのちが大事”という学校教育を真面目に受けることが生命観の健やかな発達を邪魔している恐れがあるから」、と小西さんは言います。
生命がかけがえのないものであるのはその通りですが、「生命が大事」だけを切り取ってその一点に固執すると、森や地球という全体の営みを見落とす危険性があります。例えば、実際ぐうたら村に来る学生の中には、コンビニで卵の入ったお菓子を買うのは全然平気なのに、村で母鶏が温めている卵を取って食べるのはかわいそうでできないなど、未成熟な生命観が見受けられることがあるそうです。生物は互いにかかわり合って、食べたり、食べられたり、生命をまっとうした生物の体や排泄物は分解されて、ぐるぐる回っていきます。もちろん人間もその環の中の一部です。
科学やテクノロジーですべてを理解しようとすると、こぼれ落ちてしまうことがある、と小西さんは言います。「僕の友人には図鑑の写真を撮ったり、執筆する専門家が何人もいますが、図鑑をいくら足しても森にはならないよね」と、仲間内で飲んだ時によく自虐的に言い合うんです(笑)」
「汐見先生とも話すのですが、例えば、鶏、ミミズ、水とばらばらに暗記していても仕方ない。それらを自分で結んでいけるような教育が必要だけど、つなげるだけでもまだ足りない。要は全体ってものがあるんだと。森という全体、地球という全体をどう感じるか。今後はそういう教育をもっとデザインしていく必要があると思うんです」
取材に訪れた日は、ちょうど小西さんが担当する渓谷ツアーの開催日で、村に戻ってきた保育者の皆さんが集まって振り返りをしていました。

渓谷を歩いてみて、最も印象に残ったベストシーンをそれぞれが語りました。皆さん、充実したいい表情をしていました。

・最後の急斜面は四つんばいになって登った。自分が獣になっていくような感覚があった。
・年をとると頭でばかり考えがち。今日は足先から頭まで体を使った。サワグルミについたクモの巣が美しいと思った。
・はだしで水に入った感覚が気持ち良くて、ずっと入っていたかった。
・岩にサワグルミが生えていた。無機物だと思っていた岩は、生物の苗床だった。
・イワタバコが見られた。冬のイワタバコも見たい。
・森の中にはいろんな色があって、きらきらしていた。
キッチンでいい匂いを漂わせていた蒸したてのトウモロコシがおやつに振る舞われました。私たちもおすそわけをもらいました。熱々のトウモロコシは甘くて最高でした。
 「ぜいたくに食べて。黄色いところは鶏さんが喜ぶし、軸は畑でも使える」。熱々にかぶりつきながら、何とも気持ちの良い時間が流れます
「ぜいたくに食べて。黄色いところは鶏さんが喜ぶし、軸は畑でも使える」。熱々にかぶりつきながら、何とも気持ちの良い時間が流れます
 「コロナ禍のオンラインセミナーでは、からだを通さないで生命のことを語り合う時間が増えて怖かったんですけど、今日はこうして実際にからだを通して考えた生命のことを語り合っていると安心できます(笑)」と小西さん
「コロナ禍のオンラインセミナーでは、からだを通さないで生命のことを語り合う時間が増えて怖かったんですけど、今日はこうして実際にからだを通して考えた生命のことを語り合っていると安心できます(笑)」と小西さん
 「ここでダラーッとしていたい人はいつまでもしていていいです」。解散となり、ボーッと空を眺める保育者の皆さん
「ここでダラーッとしていたい人はいつまでもしていていいです」。解散となり、ボーッと空を眺める保育者の皆さん
自然の中で過ごすと、感動と同時に怖さもあり、自分がいかにちっぽけで弱い存在かも思い知らされます。そんな正直な感想をもらす保育者の方もいました。
村では、汐見さんや小西さんの呼びかけで、エネルギーについてもできることを実践しているそうです。例えば、先ほどのぐうたラボの施設で利用する全電力は太陽光でまかなったり、地域で自伐型林業を実践する住民とつながり、枯木をもらってきて薪にしたり、雨水を貯めて利用したり、落ち葉は剪定した枝で鳥の巣のような“バイオネスト”を組んで落ち葉堆肥をつくったり−。
「今の日本の議会制民主主義の中では、自分の声は反映されないとあきらめてしまう場面も多いじゃないですか。だから汐見先生も『ここでは保育者と一緒に小さな民主主義をいっぱいやろうね』と」
自分たちにできることはささやかなことだけれども、小さなことを達成した手応えは確かに手に、心に刻まれます。
「SDGsのバックキャスティングの考え方は、夏休みの宿題を期限内に終わらせる考え方に似て、ちょっと窮屈な感じがありますよね」と小西さん。私もやっぱり宿題より、自由課題の方がやる気が出るなぁ。ぐうたら村は、保育者が子どもたちと過ごす未来がこんなだったらいいなという社会像を描きつつ、心と体を素直に動かす場所。完成図のないぐうたら村はまだ当分の間、現在進行形です。
撮影:楠聖子
地元の美術館・新聞社を経てフリーランスに。東京都国際交流委員会のニュースレター「れすぱす」、果樹農家が発行する小冊子「里見通信」、ルミネの環境活動chorokoの活動レポート、フリーペーパー「ecoshare」などの企画・執筆に携わる。Think the Earthの地球ニュースには、編集担当として2007年より参加。著書に『未来をはこぶオーケストラ』(汐文社刊)。 地球ニュースは、私にとってベースキャンプのような場所です。食、農業、福祉、教育、デザイン、テクノロジー、地域再生―、さまざまな分野で、地球視野で行動する人たちの好奇心くすぐる話題を、わかりやすく、柔らかい筆致を心がけてお伝えしていきたいと思っています!